効果音とベース [デロリアン製作記]
メインのマイコン回路を作ろうと思いますが、効果音は付けたいです。
効果音に合わせて電飾を点灯させるため、まずは効果音作りから入ります。
効果音は、電飾と連動する音に細かく分けて割り振っていきます。
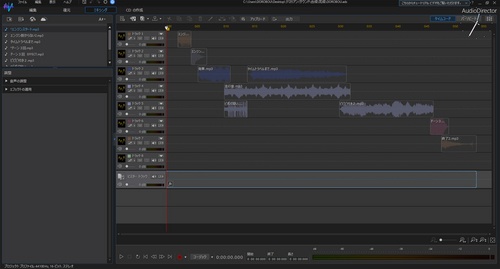
ボクはCyberLink AudioDirector 11を使って、効果音をトラック単位に分け、鳴り始める時間を把握しておきます。
どの音が何秒後から鳴るのか判るので、微調整で何度も試す方法より少ない手間でプログラムが出来ます。
もちろん、スピーカーやアンプの特性にあわせた調整や、ベースに仕込んでからの鳴りの調整も出来ますので、サウンド編集ソフトは1本持っていた方が良いですね。
サウンドは、BGMと効果音を組み合わせます。
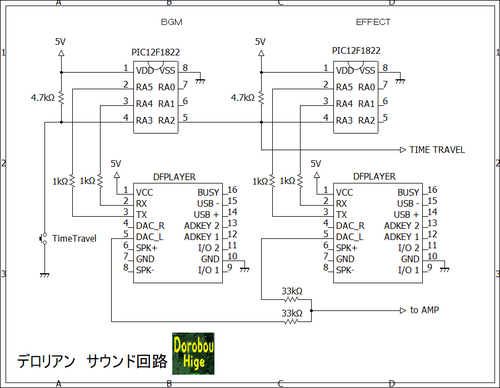
MP3プレーヤーDFPlayer mini を2個使って、SDカードに収めたMP3サウンドをPICで制御します。
PICとDFPlayerは2本の信号線でシリアル通信を行い、かなり自由にコントロールが可能です。
DFPlayerの詳しい使い方は、以前記事にしておりますので、こちらをどうぞ
https://dorobou.blog.ss-blog.jp/2019-12-29
今回はBGM用とタイムトラベル時の効果音用に分けています。
普段は映画のサントラがずっと鳴っていますが、タイムトラベル再現モードになったら、BGMの音量を絞り、効果音が再生されて、タイムトラベルが終わったらBGMの音量を戻します。
映画のシーンみたいに、バックにテーマ曲が流れている感じにしたいのです。
2つのDFPlayerからの音声出力は、33kΩの抵抗でミックスされてアンプへ出力されます。
パッシブミキサーという、とても簡単な合成方法ですが、ミキサー回路を組むほどでもない合成に便利な方法です。
組み立てた回路です。
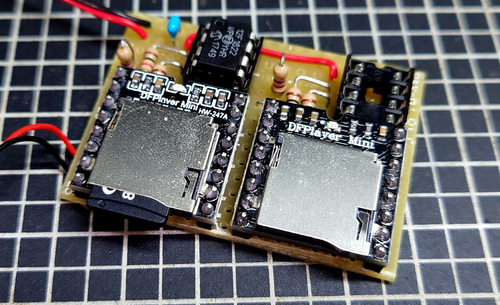
BGMを担当しているPICが、スイッチの入力を検知して効果音を担当しているPICに指令を出し、更にデロリアンのメインPICにもスイッチが押された事を知らせます。
BGM担当PICのプログラムを簡単にですがご紹介しておきますね。
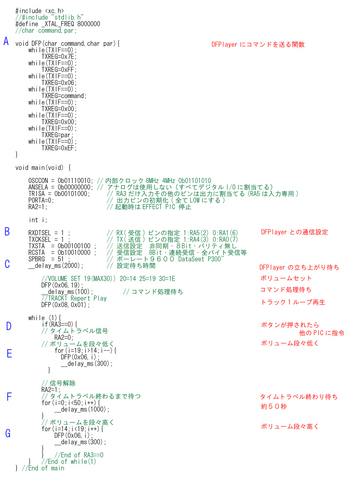
初期設定部分は省略しています。
まずAで、DFPlayerをコントロールする関数を宣言しています。
この関数に引数をセットして呼び出すだけで、DFPlayerをコントロールできます。

このコマンド表の水色部分の、左から4番目と、7番目の値をセットして呼び出します。
例えば再生(PLAY)したいなら、DFP(0x0D,0x00); と書きます。
B でシリアル通信の設定をしています。
C DFPlayerが立ち上がるのを待ちます。
どうもDFPlayerはロットによって立ち上がり時間に差があるみたいなのですが、
とりあえず2秒にしておけば大丈夫だと思います。
DFP()でコマンドを送った後も100msの待ち時間が必要になる場合があります。
D ベースのボタンが押されたら、効果音担当PICやメインPICに信号を送ります。
E BGMのDFPlayerにボリューム命令を送って、音量を下げます。
F タイムトラベルイベントが終わるまで待ちます。
G 音量をもとに戻します。
さて、サウンドはアンプで音量を上げるわけですが、会場によっては音が低すぎる場合があります。
やはり周辺に合わせてボリューム調整が出来る方が便利ですよね。
そこで、100均のUSBスピーカーに付いていたアンプを流用しようとしました。
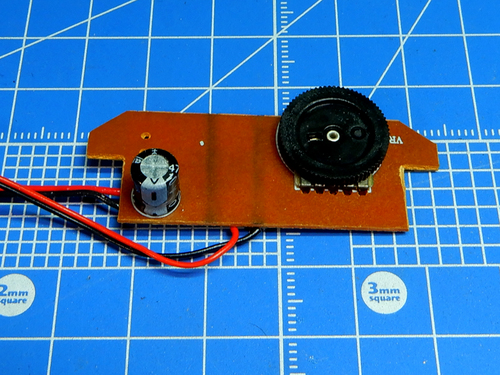
ところが、再生させてみると低音はスカスカ、音も薄くてイイマイチです。
BGMはBack to the Futureのオーケストラサウンドなので、迫力が欲しいです。
そこで、アンプを自作しました。
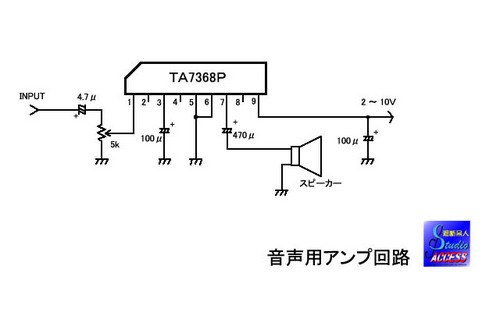
TA7368Pを使った簡単なアンプですけど、比較にならない程、音質が改善されました。
ただ、USBスピーカーのスピーカー自体はかなり高性能です。
300円なので1個150円だとしても、秋葉で同額で買ったスピーカーよりメッチャ良い音で鳴りますので、スピーカーだけは採用です。
これでサウンド関係の目処が立ちました。
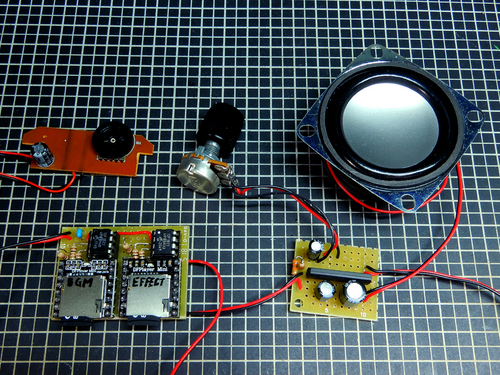
BGMと効果音を同時に流したいとか、音質が気に入らないなどと言わなければ、すぐに完成していました。
全然プラモ製作とは関係ない話で恐縮です。
デロリアンは、リモコンをやめました。
ホバーモードの切り替えを、ダイソーのリモコンライトを使って遠隔操作可能にしていましたが、そもそもリモコン化する意味があるのか?と疑問に感じてしまいました。
そのために回路は複雑化して、パーツを増やし電力を食うわけです。
別に、ベースのスイッチを押せば変形するだけで十分だろうと思い、取り外してしまいました。
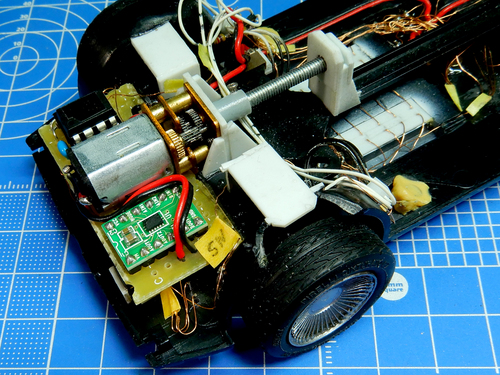
車体のスイッチは有効なので、そのスイッチを配線で引き延ばして、ベースのスイッチで操作できる様にします。
シンプルイズベストです。
タイムトラベルの開始もベースのスイッチで起動させます。
信号はベースのBGM担当PICからメインPICに伝えます
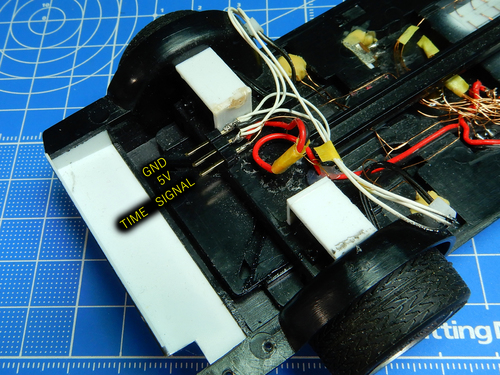
メインPICには電源とタイムトラベル信号が伝われば良いので、接続コネクタは3ピンです。
とてもシンプルな構成になりました。
ベースとの接続部分は、4ピンになります。
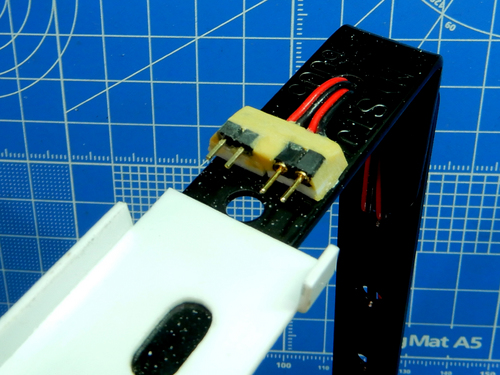
電源の5VとGNDの他、タイムトラベル信号とホバーモード切替信号の計4ピンです。
支柱にセットすれば接続される様にレイアウトしました。
ベースには、スイッチとサウンド再生回路が収まります。
100均のフタ付きケースを逆さまにして、底に1mmプラ板を貼って平面にしました。
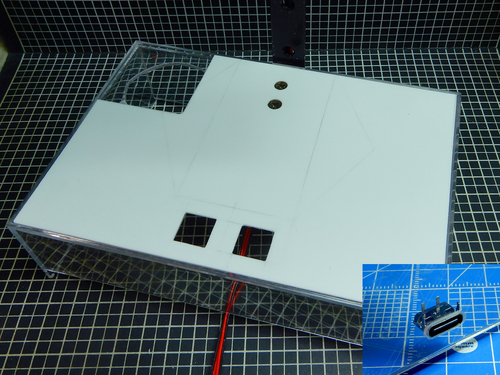
支柱はネジ留めでガッチリ支えてもらいます。
スイッチ用の穴、スピーカー用の穴、背面に電源供給用のUSB Type-C端子を付けました。
このケースは元々フタが付いていたので、前面と背面にスキマが出来ます。
そこから音が漏れて、バスレフとしても効果があります。
スイッチを2個取り付けます。
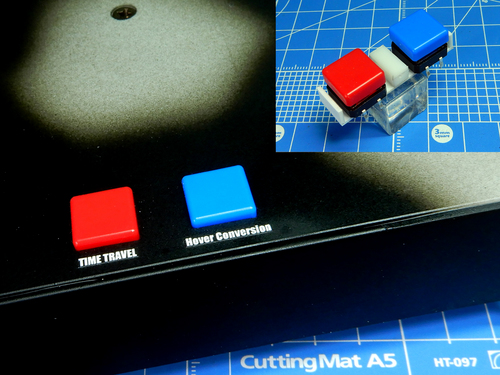
プッシュスイッチをプラ板の支えに固定して取り付けました。
塗装後に、PCで印刷したラベルを貼り付けてレタリングしています。
デロリアンの操作は、たった2個のスイッチで操作する事になります。
あとはマイコンがやってくれるわけですね。
100均のミラーを用意しました。
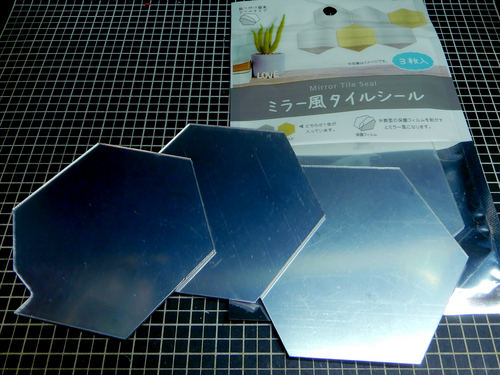
ベースの上面には、100均で見付けた、ミラー型タイルシールを貼ろうと思います。
6角形で未来的ですし、飛行状態で車体下の電飾も良く見える様になります。
完成するとこんな感じです。

これからベース内部にサウンド回路を仕込みますので、ミラータイルはまだ貼っていません。
表面の保護シートも剥がしていません。
もうちょっとカッコ良く作りたかったのですが、機能としては十分ですかね。
とりあえずベースが形になったので、これでやっとメインPICの製作に移れます。
効果音に合わせて電飾を点灯させるため、まずは効果音作りから入ります。
効果音は、電飾と連動する音に細かく分けて割り振っていきます。
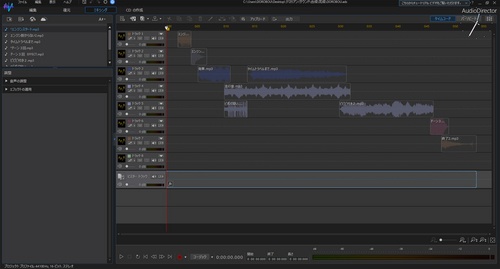
ボクはCyberLink AudioDirector 11を使って、効果音をトラック単位に分け、鳴り始める時間を把握しておきます。
どの音が何秒後から鳴るのか判るので、微調整で何度も試す方法より少ない手間でプログラムが出来ます。
もちろん、スピーカーやアンプの特性にあわせた調整や、ベースに仕込んでからの鳴りの調整も出来ますので、サウンド編集ソフトは1本持っていた方が良いですね。
サウンドは、BGMと効果音を組み合わせます。
MP3プレーヤーDFPlayer mini を2個使って、SDカードに収めたMP3サウンドをPICで制御します。
PICとDFPlayerは2本の信号線でシリアル通信を行い、かなり自由にコントロールが可能です。
DFPlayerの詳しい使い方は、以前記事にしておりますので、こちらをどうぞ
https://dorobou.blog.ss-blog.jp/2019-12-29
今回はBGM用とタイムトラベル時の効果音用に分けています。
普段は映画のサントラがずっと鳴っていますが、タイムトラベル再現モードになったら、BGMの音量を絞り、効果音が再生されて、タイムトラベルが終わったらBGMの音量を戻します。
映画のシーンみたいに、バックにテーマ曲が流れている感じにしたいのです。
2つのDFPlayerからの音声出力は、33kΩの抵抗でミックスされてアンプへ出力されます。
パッシブミキサーという、とても簡単な合成方法ですが、ミキサー回路を組むほどでもない合成に便利な方法です。
組み立てた回路です。
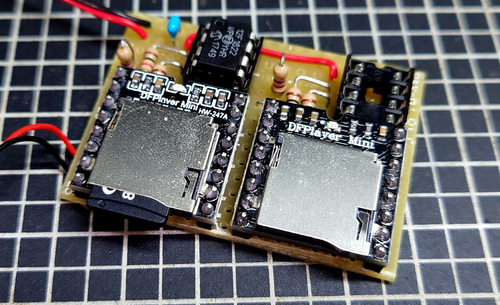
BGMを担当しているPICが、スイッチの入力を検知して効果音を担当しているPICに指令を出し、更にデロリアンのメインPICにもスイッチが押された事を知らせます。
BGM担当PICのプログラムを簡単にですがご紹介しておきますね。
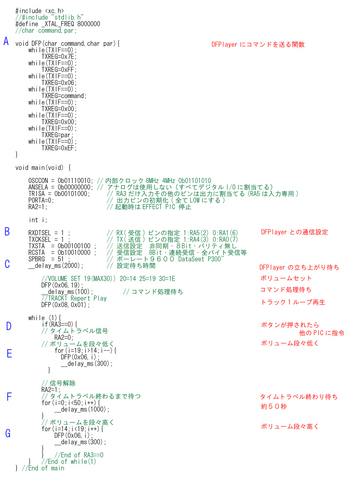
初期設定部分は省略しています。
まずAで、DFPlayerをコントロールする関数を宣言しています。
この関数に引数をセットして呼び出すだけで、DFPlayerをコントロールできます。

このコマンド表の水色部分の、左から4番目と、7番目の値をセットして呼び出します。
例えば再生(PLAY)したいなら、DFP(0x0D,0x00); と書きます。
B でシリアル通信の設定をしています。
C DFPlayerが立ち上がるのを待ちます。
どうもDFPlayerはロットによって立ち上がり時間に差があるみたいなのですが、
とりあえず2秒にしておけば大丈夫だと思います。
DFP()でコマンドを送った後も100msの待ち時間が必要になる場合があります。
D ベースのボタンが押されたら、効果音担当PICやメインPICに信号を送ります。
E BGMのDFPlayerにボリューム命令を送って、音量を下げます。
F タイムトラベルイベントが終わるまで待ちます。
G 音量をもとに戻します。
さて、サウンドはアンプで音量を上げるわけですが、会場によっては音が低すぎる場合があります。
やはり周辺に合わせてボリューム調整が出来る方が便利ですよね。
そこで、100均のUSBスピーカーに付いていたアンプを流用しようとしました。
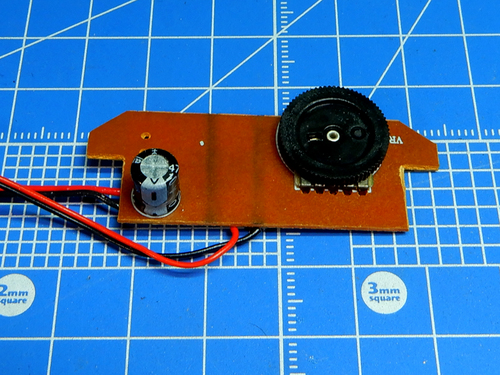
ところが、再生させてみると低音はスカスカ、音も薄くてイイマイチです。
BGMはBack to the Futureのオーケストラサウンドなので、迫力が欲しいです。
そこで、アンプを自作しました。
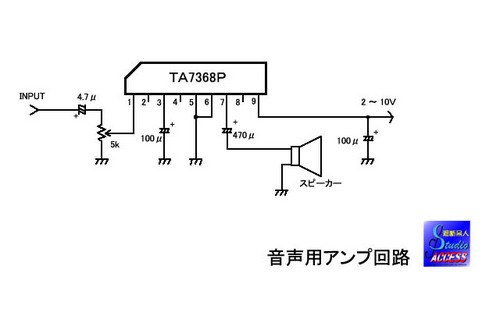
TA7368Pを使った簡単なアンプですけど、比較にならない程、音質が改善されました。
ただ、USBスピーカーのスピーカー自体はかなり高性能です。
300円なので1個150円だとしても、秋葉で同額で買ったスピーカーよりメッチャ良い音で鳴りますので、スピーカーだけは採用です。
これでサウンド関係の目処が立ちました。
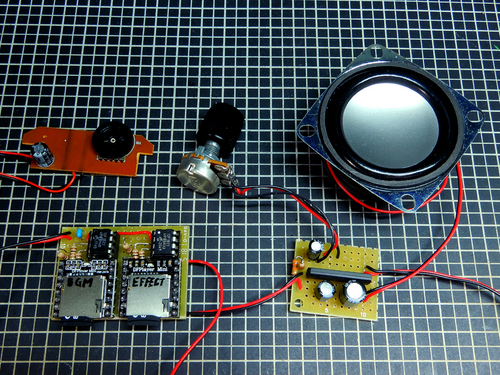
BGMと効果音を同時に流したいとか、音質が気に入らないなどと言わなければ、すぐに完成していました。
全然プラモ製作とは関係ない話で恐縮です。
デロリアンは、リモコンをやめました。
ホバーモードの切り替えを、ダイソーのリモコンライトを使って遠隔操作可能にしていましたが、そもそもリモコン化する意味があるのか?と疑問に感じてしまいました。
そのために回路は複雑化して、パーツを増やし電力を食うわけです。
別に、ベースのスイッチを押せば変形するだけで十分だろうと思い、取り外してしまいました。
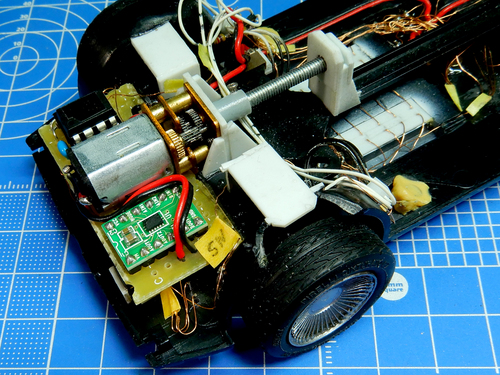
車体のスイッチは有効なので、そのスイッチを配線で引き延ばして、ベースのスイッチで操作できる様にします。
シンプルイズベストです。
タイムトラベルの開始もベースのスイッチで起動させます。
信号はベースのBGM担当PICからメインPICに伝えます
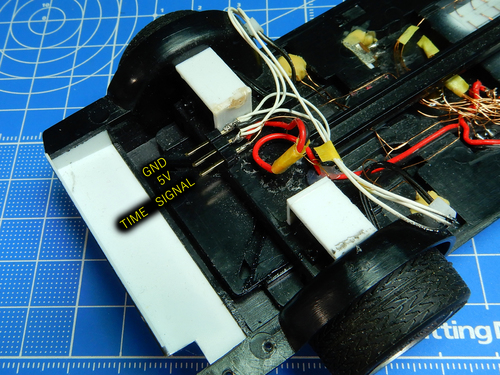
メインPICには電源とタイムトラベル信号が伝われば良いので、接続コネクタは3ピンです。
とてもシンプルな構成になりました。
ベースとの接続部分は、4ピンになります。
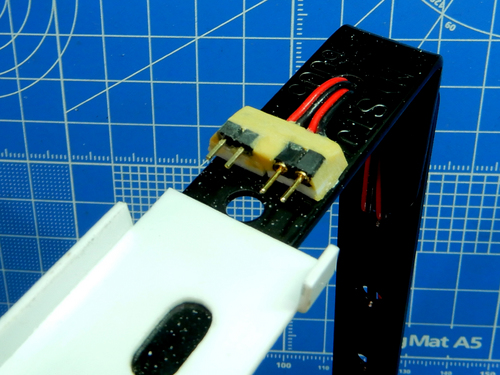
電源の5VとGNDの他、タイムトラベル信号とホバーモード切替信号の計4ピンです。
支柱にセットすれば接続される様にレイアウトしました。
ベースには、スイッチとサウンド再生回路が収まります。
100均のフタ付きケースを逆さまにして、底に1mmプラ板を貼って平面にしました。
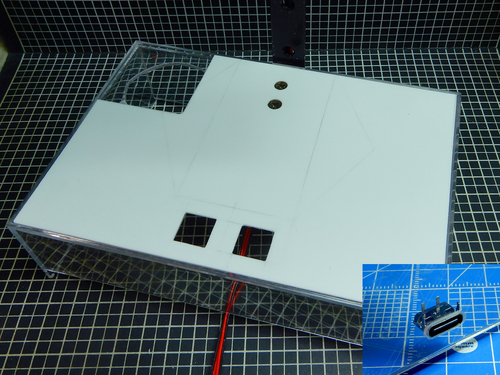
支柱はネジ留めでガッチリ支えてもらいます。
スイッチ用の穴、スピーカー用の穴、背面に電源供給用のUSB Type-C端子を付けました。
このケースは元々フタが付いていたので、前面と背面にスキマが出来ます。
そこから音が漏れて、バスレフとしても効果があります。
スイッチを2個取り付けます。
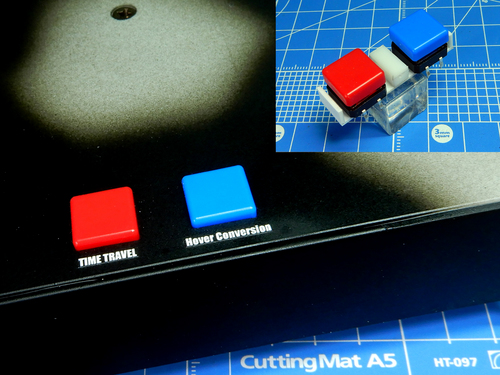
プッシュスイッチをプラ板の支えに固定して取り付けました。
塗装後に、PCで印刷したラベルを貼り付けてレタリングしています。
デロリアンの操作は、たった2個のスイッチで操作する事になります。
あとはマイコンがやってくれるわけですね。
100均のミラーを用意しました。
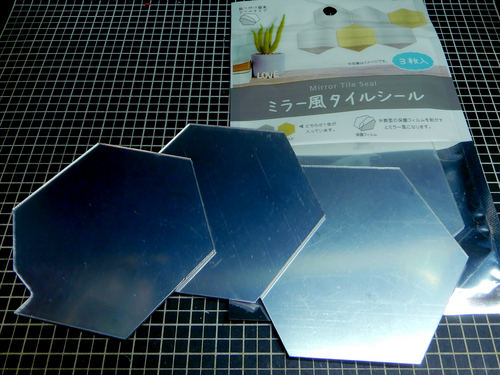
ベースの上面には、100均で見付けた、ミラー型タイルシールを貼ろうと思います。
6角形で未来的ですし、飛行状態で車体下の電飾も良く見える様になります。
完成するとこんな感じです。

これからベース内部にサウンド回路を仕込みますので、ミラータイルはまだ貼っていません。
表面の保護シートも剥がしていません。
もうちょっとカッコ良く作りたかったのですが、機能としては十分ですかね。
とりあえずベースが形になったので、これでやっとメインPICの製作に移れます。
2022-04-10 20:52
コメント(0)
















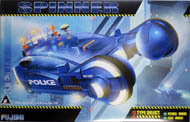



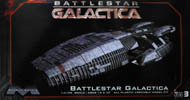








































 2007-06-06 完成しました。
2007-06-06 完成しました。
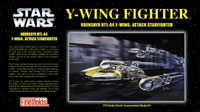 2007-08-21 完成しました。
2007-08-21 完成しました。

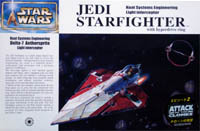
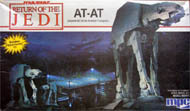
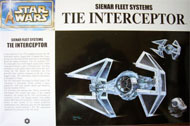

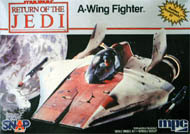

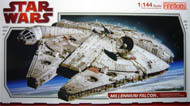










 2007-06-22 完成しました。
2007-06-22 完成しました。
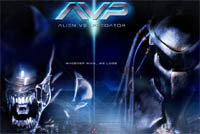
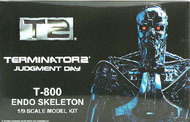




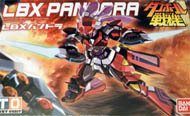
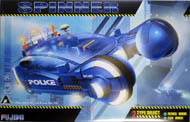

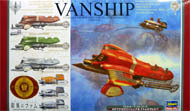

 2007-03-03 完成しました。
2007-03-03 完成しました。
 2007-03-12 完成しました♪
2007-03-12 完成しました♪
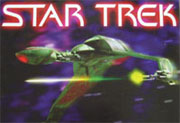 2007-07-08 完成しました♪
2007-07-08 完成しました♪

 2005-12-18 完成しました♪
2005-12-18 完成しました♪
 2008-06-05 完成しました♪
2008-06-05 完成しました♪
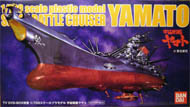 2010-04-05 完成しました。
2010-04-05 完成しました。
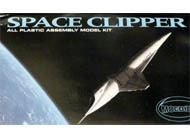



コメント 0